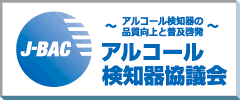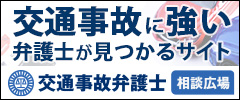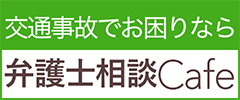全日本交通安全協会の歴史
全国交通安全協会のこれまでの歴史を振り返りながら、現在に至るまでの沿革をご紹介します。
| 年 | 月日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1950年 (昭和25年) |
10月17日 | 日本交通安全協会設立発起人会開催(於 斉藤昇(昭和22年第60代警視総監、後初代警察庁長官)国家地方警察本部長官公邸)(発起人:辻二郎国家公安委員会委員長他12人) |
| 11月6日 | 設立総会開催 | |
| 12月6日 | 日本交通安全協会設立 | |
| 初代会長に福島元吉氏(東京交通安全協会会長)が就任 | ||
| 事務所を警視庁内(3階)に設置 | ||
| 1956年 (昭和31年) |
7月23日 | 事務所移転(警視庁5階へ) |
| 1960年 (昭和35年) |
7月18日 | 事務所を新宿区の元神楽坂警察署跡に移転 |
| 8月1日 | 事務所を千代田区平河町2-9 都市計画会館内に移転 | |
| 12月1日 | 日本交通安全協会解散 | |
| 12月2日 | 財団法人全日本交通安全協会の設立を決議 | |
| 1961年 (昭和36年) |
1月10日 | 財団法人全日本交通安全協会 設立許可 |
| 初代会長に津島寿一氏(元大蔵大臣・参議院議員/日本交通安全協会会長)が就任 | ||
| 1979年 (昭和54年) |
11月10日 | 事務所を現在地に移転(九段南4-8-13自動車会館7F) |
| 1998年 (平成10年) |
4月1日 | 全国交通安全活動推進センターに指定(国家公安委員会) |
| 2013年 (平成25年) |
4月1日 | 一般財団法人全日本交通安全協会に移行 |
交通安全協会の誕生
わが国の交通機関は、明治に入って急速に発達し、それまでの駕龍や馬の背から馬車、人力車、乗合馬車、軌道馬車、自転車、自動車、路面電車へと変化しました。特に明治30年代に輸入された自動車は、大正から昭和に入って発達し、人々は直接、間接その恩恵を受けるようになりましたが、その反面、交通事故も次第に増加しはじめました。このため各種の法規が制定され、なかでも、大正8年1月に運転免許制度などを定めた自動車取締令(内務省令第1号)、大正9年12月に人も車も左側通行などを定めた道路取締令(内務省令第45号)が全国統一の交通法規としてはじめて制定、公布されました。
これらの法令の周知徹底のために、警察が中心となって「交通安全運動」が展開されるとともに、民間の交通安全活動を組織的に推進するため、警察の指導により、広島、静岡、岐阜、福岡、愛知などの府県で「交通安全協会」が結成されはじめました。
昭和8年8月、自動車取締令が全面的に改正され、運転免許制度、自動車の構造装置、運転者の遵守事項等について詳細な規則が設けられ、交通事故の防止が図られました。
わが国の本格的な自動車交通が幕明けとなったのは戦後のことで、年とともに進展する産業と経済活動は、必然的に輸送需要を急速に増大させるに至り、道路交通、特に自動車による輸送の必要性がクローズアップされました。同時に、交通事故も多発しはじめ、事故防止の問題が世論となって盛り上がってきました。
このような交通事情と世論を反映して、地方の道路運送業者、自家用自動車の所有者、運転者等を会員とする「交通安全協会」の設立が全国各地で進められました。
日本交通安全協会の設立一全国統一運動の確立
その後、経済活動の一層の活発化に伴い、自動車交通が広域化し、交通事故の防止対策も、全国統一的な交通安全運動を強力、かつ、幅広く推進することの必要性が痛感されるに至りました。このため国家公安委員会(辻 二郎委員長)では、全国12ブロックの代表都道府県交通安全協会(連合会)会長と共に中央団体の設立を企図し、当時の国家地方警察本部警ら交通課がその事務の推進に当たりました。
このようにして関係者の努力が実り、昭和25年11月6日、東京・上野の精養軒において設立総会が開かれ、都道府県交通安全協会、大都市交通安全協会、国家公安委員会および警察関係者を会員とする日本交通安全協会が設立されました。会長に福島元吉氏(東京交通安全協会会長)が就任、事務所を警視庁内に置きました。
その後、昭和27年4月に第2代会長に早川慎一氏が、続いて昭和31年9月に第3代会長に津島寿一氏が就任し、事務所は、昭和35年7月、都内新宿区の元神楽坂警察署跡に移り、同年9月に千代田区平河町2-9 都市計画会館内に移転しました。
なお、昭和29年6月、警察法の改正により六大都市警察を除く自治体警察が国家地方警察に統合され、さらに昭和30年6月に六大都市自治体警察も解消して都道府県単位の警察に統合されたので、交通安全協会も都道府県単位に一本化され(横浜市のみ例外として存続)、日本交通安全協会の組織構成員となりました。
また、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図るため、昭和23年12月10日から16日までの1週間、国家地方警察本部の主催により全国交通安全運動が実施され、昭和27年の運動から日本交通安全協会は主催団体に加わり、その後、実施期間や春秋2回実施など実施要綱に変更を加えながら現在に至っています。
日本交通安全協会設立趣意書(原文のまま)
文化国家、道義国家として祖国を再建することは、現代の日本国民に課せられた最大の使命であります。
ひるがえって、わが国現下の交通状態をみるに、甚だ残念なことでありますが、到底文化国家にふさわしいものと申すわけにはまいりません。交通道徳、交通施設等が充分でなく、ともすれば交通の秩序は失われ勝ちであります。交通事故も年とともに増加の一途をたどっており、昨年度の統計によりますと、事故件数61,606件、死者6,715名、負傷者27,558名の多数に上っているのであります。すなわち、これを一日平均にいたしますと毎日、わが国のどこかで、94名の犠牲者を出している勘定になり、交通事故による貴重な人命の損傷数は、新聞紙上を賑わす凶悪な刑事事件、工場災害、火災、天災等によるものの遥かに及ばない大きなものなのであります。
この恐ろしい交通事故を防止して、交通の安全と円滑を図り、街々に明るい交通秩序を生み出すことこそ文化国民たらんとするわれわれの貴い義務でなければなりません。私達は、各地の交通安全協会にあって、及ばずながらこのために努力してまいったのでありますが、交通というものの性質から見ましても最近の交通の実情から見ましても、われわれの努力を全国的規模にまで拡大強化し、科学的な調査研究と強力な安全運動とを展開して飛躍的な成果を期する必要があることを痛感している次第であります。
このような趣旨によりまして、国際水準に劣らない交通体制をつくり上げる念願のもとにここに日本交通安全協会を設立し、交通安全に関する各種の事業を推進して、明るい交通秩序を生み出すために微力を尽したいと存ずるものであります。
各位の御賛同を御願いする次第であります。
昭和25年11月
発起人
国家公安委員長 辻 二郎
(以下氏名を省略)
財団法人「全日本交通安全協会」の発足
日本交通安全協会結成後も交通事故は増加の一途をたどり、特に、昭和33年は、交通事故の発生件数が16万8,000件にも達し、また、死者数も8,000人を超えました。こうした交通事情の悪化に対処すべく、政府をはじめ関係行政機関はその対策を種々強化しましたが、この年の4月22日の国会で、衆議院地方行政委員会が人命の損傷等被害の大きいことを憂慮し、12項目にわたる「交通事故防止に関する決議」を行いました。この決議の中に、交通安全協会の刷新強化の問題が特に取り上げられ、「交通安全協会の組織を刷新し、その活動を拡充強化して、交通事故による被害者の救済等にも努力するよう指導すること」と強調されました。
翌昭和34年には、交通事故の発生件数が20万件、死亡者は1万人を超えるに至り、昭和35年には、昭和22年制定の「道路交通取締法」を廃止し、交通の安全と円滑を目的とした道路交通法が制定(6月25日公布、12月20日施行)されました。こうした状況の下、日本交通安全協会は創立10周年を機に組織を発展的に解消することを決定し、同年12月1日に解散、翌12月2日、東京・千代田区の東京会館において財団法人「全日本交通安全協会」設立を決議し(財団法人の許可は昭和36年1月10日)、初代会長に元大蔵大臣・参議院議員の津島寿一氏(日本交通安全協会会長)が就任しました。
なお、当協会は平成25年4月1日、「一般財団法人 全日本交通安全協会」に移行しました。
財団法人全日本交通安全協会設立趣意書
最近における自動車の飛躍的な激増にともない、交通事故は逐年急激に増加の一途をたどり、まことに深憂にたえないものがあり、世論もまた、交通事故防止と、交通秩序の確立に大きな関心を示し、これが対策は今や国家的な重要問題の一つになってきたところである。交通事故を防止し、交通秩序を確立するためには、交通環境の整備、行政機関による適切な措置が必要であることは論をまたないところであるが、最も根本的な問題は、国民の一人一人の交通道徳を高めることに帰着する。この目的達成のために、当協会はつとに警察と表裏一体となって努力してきたのであるが、更にこの度国民の要望によって成立した新しい道路交通法の実施を機会に、広く国民各層の理解と協力による一大国民運動を展開することが必要であると信ずる。この国民の問から盛り上る交通安全に対する鮮烈な声を国民運動にまで組織化するための中核体となるものは、他ならぬ日本交通安全協会でなければならないと思料する。
この重大な任務を果すためには、現在の協会を飛躍的に拡大強化することが緊急の要務である。この当面の要請に応えるために、現在の日本交通安全協会を発展的に解消せしめ、その清算によって生ずる残余金を寄付資産として、更に国民各層の協力を組織し具体化し得る内部機構を整え、新に財団法人全日本交通安全協会を設立せんとするものである。
昭和36年1月10日
全国交通安全活動推進センターとして指定
当協会は、昭和62年4月1日、道路交通法に基づいて国家公安委員会から「全国道路使用適正化センター」に指定され、車両の駐車、その他道路使用の適正化を図るための広報啓発及び調査研究等の諸活動を推進してきましたが、平成9年5月に改正された道路交通法(第108条の32)に基づき、同センターが「全国交通安全活動推進センター」に改組されました。平成10年4月1日、当協会が国家公安委員会から当該全国センターとして指定されたことに伴い、以降、従来の道路使用の適正化を図るための業務のほか、交通安全に関する広報啓発活動、交通事故相談、運転適性指導、その他都道府県交通安全活動推進センターの業務を行う者に対する研修、各分野の交通安全教育指導担当者等に対する研修及び都道府県センターの事業についての連絡調整等の業務を推進しています。
創立50周年記念事業
当協会は昭和36年1月10日に設立され、平成23年1月で満50周年を迎えました。そこで、創立50周年記念事業として、「全日本交通安全協会50年のあゆみ」を発刊するとともに、「創立50周年記念シンポジウム」を開催しました。
記念誌「全日本交通安全協会50年のあゆみ」の発刊
創立から50年間の歴史と活動をまとめたもので、序章(交通安全運動の源流から協会創立前夜まで)、第1章(全日本交通安全協会の設立時の活動)、第2章(設立10年を経て着実に現れた成果)、第3章(国民皆免許時代の新たな課題に対応)、第4章(21世紀に向けての交通安全対策の確立)、第5章(交通事故ゼロの理想達成へ)の歴史編と、当協会が現在実施している活動をまとめた事業概要編、当協会や交通関係の動き、社会情勢から構成されている年表からなっています。サイズはA4版120ページ、500部を作成し、会員、交通関係機関・団体等に配布しました。
創立50周年記念シンポジウムの開催
平成23年1月17日(月)、東京・新宿区市谷のホテルグランドヒル市ヶ谷で「全日本交通安全協会創立50周年記念シンポジウム」を開催しました。
シンポジウムのテーマは、「人と車を見つめて50年~そしてこれからの展望~」で、交通関係機関・団体の関係者、学識者など約600人が出席。第1部では鈴木春男千葉大学名誉教授が「交通安全への動機づけ」と題して基調講演を、第2部では「地域の仲間づくりを交通安全にどう生かすか」というテーマでパネルディスカッションを行いました。
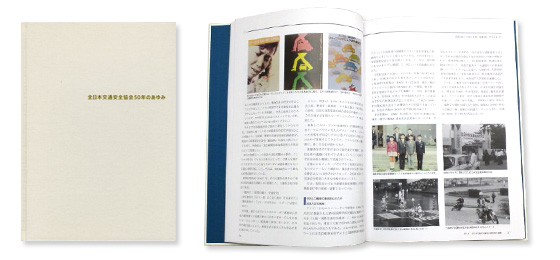
「全日本交通安全協会50年のあゆみ」

パネリストによるディスカッション
歴代会長
昭和36年1月に財団法人全日本交通安全協会となり、初代会長に津島寿一氏(元大蔵大臣、防衛庁長官)が就任。以後、昭和42年3月永野重雄氏(富士製鐵株式会社社長、日本商工会議所会頭)、同59年6月今里廣記氏(日本精工株式会社相談役、東京交通安全協会会長)、同60年7月武田豊氏(新日本製鐵株式会社社長)、平成3年6月平岩外四氏(東京電力株式会社会長、(社)経済団体連合会会長)、同15年1月那須翔氏(東京電力株式会社顧問)、同16年3月今井敬氏(日本製鉄株式会社名誉会長、(一社)日本経済団体連合会名誉会長)、令和3年6月30日、川村隆氏(株式会社日立製作所名誉会長)、令和7年7月8日、現会長宗岡 正二(日本製鉄株式会社社友)が会長に就任しました。
組織体制・交通安全事業の拡充強化
新協会の発足に伴って、従来の組織が大幅に拡充強化され、現在の体制が確立しました。この間、交通安全国民運動中央大会の開催(昭和36年)、交通栄誉章「緑十字章」の制定(昭和36年)、全日本交通安全ニュースの創刊(昭和36年)、交通安全マークの制定(昭和37年)、小・中学生の交通事故防止アイディア・コンテストの実施(昭和38年)、全国学校交通安全研修大会の開催(昭和38年)、交通安全宣言都市連絡協議会の開催(昭和38年)、「交通事故から頭を守ろう」運動の推進(昭和39年)、交通安全年間スローガンの募集(昭和40年、昭和46年からはスローガン入りポスターデザインも募集)、交通安全教育推進誌「人と車」の創刊(昭和40年)、ヨーロッパ交通事情視察団の派遣(昭和40年)、交通事故物故者慰霊祭の開催(昭和40年)、交通安全子供自転車全国大会(昭和41年)、二輪車安全運転全国大会(昭和43年)等の諸行事等を実施して基礎を固めました。
全日本交通安全協会と都道府県交通安全協会との関係
当協会と、都道府県交通安全協会(以下「県安協」といいます。)は、それぞれ独自に発達してきた組織です。また、各県安協においても、一般財団法人、一般社団法人や公益財団法人の形態をとるものがあり、組織構造、財政、事業内容、地区安全協会との関係等が様々となっています。
このような中、交通の危険防止のための交通道徳の普及高揚を図り、もって交通秩序の確立と交通安全の実現に寄与するため、県安協では、全国津々浦々での交通安全活動を展開しており、当協会は、県安協の活動を支援・サポートする役割を担っております。
具体的には、交通安全国民運動中央大会の開催、交通安全栄誉章の授与、交通安全こども自転車全国大会の開催、交通安全ポスターの制作と配付、交通安全利用資機材の配付、交通安全教育指導者等の研修等を行っています。併せて、これら事業を円滑かつ堅実に展開するために、全国専務理事等会議などを通じ、各県安協において抱える課題等につき、情報共有を図ると共に、課題への取組み方策などについて検討を続けています。
また、当協会は、道路交通法(第108条の32)に基づき、国家公安委員会から全国交通安全活動推進センターとして指定され、県安協は、同法(第108条の31)に基づき都道府県交通安全活動推進センターとして指定を受けています。そのため、当協会において、交通安全に関する広報啓発活動、交通事故相談、運転適性指導、その他都道府県交通安全活動推進センターの業務を行う者に対する研修、各分野の交通安全教育指導担当者等に対する研修及び都道府県交通安全活動推進センターの事業についての連絡調整等の業務を行っています。
このように、当協会、県安協は、密接な関係を有しており、交通事故のない、明るい住みよい交通社会を目指すために、軌を一にして活動を展開しています。
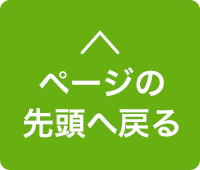
掲載ご希望の企業、団体等におかれましては、当協会の「 >バナー広告利用規約」をご確認の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
(一財)全日本交通安全協会 総務課
電話:03(3264)2641(代表)